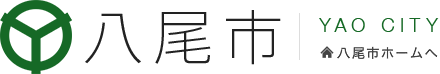[2022年11月11日]
ID:53125
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自転車の危険行為15項目について
道路交通法により、自転車の危険行為15項目が規定されています。
自転車を運転中に、この危険行為を繰り返した(3年間に2回以上の摘発)場合、自転車運転者講習の受講が義務化されており、受講しないと5万円以下の罰金が定められています。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反(道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(道路の中央から右側部分を通行する行為など)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為)
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等(優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
- 交差点優先車妨害等(交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為)
- 環状交差点安全進行義務違反等(環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反(歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為)
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為) ※携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。
- 他の運転を妨害する運転(あおり運転)
お問い合わせ
八尾市 都市整備部 都市交通課
電話: 072-924-3880 ファックス: 072-924-0207