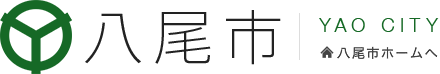[2023年9月27日]
ID:62607
公金受取口座登録制度とは(デジタル庁)
この制度は、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人につき一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する(給付金の受取専用の口座を予め登録しておく)ことを言います。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になり、迅速な給付の実現につながる可能性があります。
この登録される口座を、公的給付支給等口座=公金受取口座(公金口座)と言います。
なお、公金口座に登録できる金融機関は、デジタル庁にて公開されておりますので、ホームページをご覧ください。
公金受取口座登録が可能な金融機関(銀行)(別ウインドウで開く)
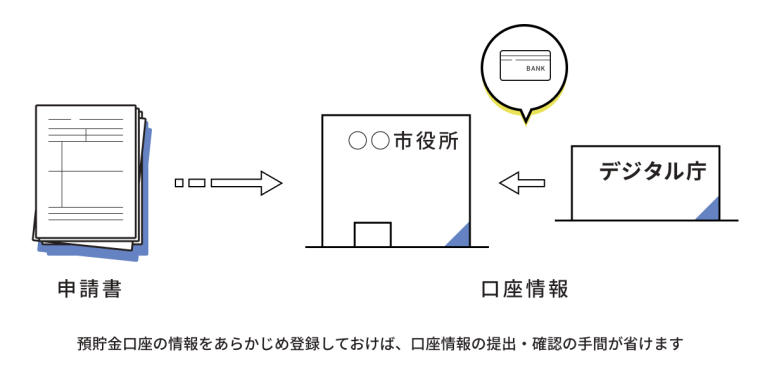
(デジタル庁ホームページより)
公金受取口座の登録について
公金受取口座の登録は、パソコンやスマートフォンを利用して登録することができます。
登録に必要なもの
- (必須)本人のマイナンバーカード
- (必須)マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(4桁の数字による暗証番号 ※受取時に設定した数字)
- (いずれか)スマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー
- (スマートフォンの場合)マイナポータルアプリ ※古い機種等の場合、登録できない場合があります。
- (必須)本人名義の金融機関の情報(金融機関名・支店・口座番号等)
公金受取口座の登録は、下記の方法より登録することができます。
- 確定申告コーナー(別ウインドウで開く)(国税局)
- マイナポータル(別ウインドウで開く)(デジタル庁)
- 令和5年度後半開始予定 各金融機関(銀行等)の窓口等
マイナポータルにアクセスする場合、スマートフォンを利用して、下記の「マイナポータルアプリ」をインストールする方法が便利です。
- アップルストア(別ウインドウで開く)(iPhoneの場合)
- グーグルストア(別ウインドウで開く)(Androidの場合)
よくある質問
Q0. 公金口座の登録に必要なものは何か
A.「マイナンバーカード」と「金融機関の銀行名、支店名、口座番号と名義が分かるもの(通帳やキャッシュカード)」、マイナンバーカードの「利用者証明用暗証番号(※カード作成時にご自身で設定した4桁の暗証番号)」が必要です。(いずれかが不足する場合(不明な場合)登録できません。)
公金口座の登録には、登録する本人のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は口座の登録はできません。公金口座の登録を希望する場合、まずはマイナンバーカードの申請から行ってください。
Q1.どこで公金口座を登録できるのか
A.パソコンにカードリーダーがある(付いている)インターネット環境か、ご自身等のスマートフォンよりマイナポータル(WEBサイト)にアクセスの上、登録することができます。なお、2023年後半からは、各金融機関窓口での登録ができるようになる予定です。
Q2.ガラケー(いわゆる携帯電話)しかなく、家にカードリーダーもない
A.スマートフォンのアプリであれば、他人のスマートフォンからでも登録ができます。マイナポータルのアプリには個人情報は記録されないため(その都度、個人のマイナンバーカードで暗証番号を用いて認証する仕組みのため)、ご家族等が対応するスマートフォンをお持ちであれば、そのスマートフォンにアプリをインストールすることで本人以外の公金口座も登録をすることができます。
ただし、個人の口座情報を入力する必要があるため、なるべく、ご家族等の身内の方のスマートフォンを利用することが推奨されます。
Q3.市役所に行けば公金口座の登録はできるのか
A.公金口座の登録は国への登録となるため、市役所に専用の窓口はございません。Q1のとおりとなります。
※その為、登録した情報等も含めて、公金口座の内容に関することを市役所にお問い合わせいただいても、一切、お答えはできません。
Q4.公金口座の登録を代理ですることは可能か
A.本人の意思により行う必要があるため、ご家族も含めて、代理人による登録は一切認められておりません。
例えば、親の公金口座の登録手続きを子が代理で行うことはできません。ただし、本人が登録を希望する場合で、同席の上で、スマートフォン等の端末操作についてのみを本人に代わって第三者が行うことは可能です。
なお、15歳未満の子の口座登録を行う場合は、法定代理人(=親権者)による登録が可能です。ただし、この場合でも法定代理人以外の代理人が登録することは認められません。
参考:口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約(別ウインドウで開く)(第6条)
Q5.登録できる口座は本人のものか
A.15歳未満の子の登録をする場合も含め、必ず本人名義の口座である必要があります。その為、口座を所有していない方は、公金口座の登録はできません。また、屋号(〇〇会社、など)や肩書(職種)が入っているものも登録はできません。
つまり、八尾 太郎さんが登録できる公金口座の名義は、八尾 太郎(または、ヤオ タロウ)に限られます。なお、通帳を発行しないネットバンク等でも登録ができます。
Q6.公金口座に指定した金融機関の口座の変更等はできるのか
A.マイナポータルから変更や削除ができます。マイナポータルへのアクセスは、ご自身のスマートフォンやインターネット環境よりアクセスをお願いします。
※市役所では変更に関する手続はできません。
Q7.公金口座を登録したくない、または、公金口座は登録しなければならないのか
A.公金口座はあくまで任意の制度ですので、本人が希望しない場合、登録する必要はありません。また、公金口座を登録しないと受け取れない(公金口座の登録が支給要件である)給付金等も2023年2月時点では存在しません。
したがって、制度の趣旨をよく理解いただき、登録をする・しないの判断は、あくまでご自身でその判断を行ってください。
※市役所や公的機関、金融機関から、公金口座への登録を強制・要件とすることは一切ありません。
Q8.制度の事がよくわからない、もっと詳しく知りたい
A.国にてフリーダイヤルが設置されておりますので、下記のフリーダイヤルへお電話ください。なお、市役所では公金口座の一切についてお答えはできません。
Q9.任意の制度なのに、年金事務所などに登録している銀行の口座が強制的に登録されると聞いたが
A.改正番号法により、公金口座の登録をされていない場合、当該行政機関(年金機構や自治体など)より、未登録者に対し「文書」で登録に関する案内の送付があります。この文書を期限内に返送しない(同意や不同意の意思表示をしない)場合にのみ登録に同意したものとみなす制度が予定されております。
つまり、当該行政機関に対し、期限内に登録に同意しない旨を回答(返送)すれば、当該行政機関に提出している口座が公金口座に登録されることはありません。
これは、迅速な公金の給付を実現するべく、政府(国)が導入を目指している制度ですので、当該趣旨をご理解の上、個人の意思表示をお願いします。
A.「マイナンバーカード」と「金融機関の銀行名、支店名、口座番号と名義が分かるもの(通帳やキャッシュカード)」、マイナンバーカードの「利用者証明用暗証番号(※カード作成時にご自身で設定した4桁の暗証番号)」が必要です。(いずれかが不足する場合(不明な場合)登録できません。)
公金口座の登録には、登録する本人のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は口座の登録はできません。公金口座の登録を希望する場合、まずはマイナンバーカードの申請から行ってください。
Q1.どこで公金口座を登録できるのか
A.パソコンにカードリーダーがある(付いている)インターネット環境か、ご自身等のスマートフォンよりマイナポータル(WEBサイト)にアクセスの上、登録することができます。なお、2023年後半からは、各金融機関窓口での登録ができるようになる予定です。
Q2.ガラケー(いわゆる携帯電話)しかなく、家にカードリーダーもない
A.スマートフォンのアプリであれば、他人のスマートフォンからでも登録ができます。マイナポータルのアプリには個人情報は記録されないため(その都度、個人のマイナンバーカードで暗証番号を用いて認証する仕組みのため)、ご家族等が対応するスマートフォンをお持ちであれば、そのスマートフォンにアプリをインストールすることで本人以外の公金口座も登録をすることができます。
ただし、個人の口座情報を入力する必要があるため、なるべく、ご家族等の身内の方のスマートフォンを利用することが推奨されます。
Q3.市役所に行けば公金口座の登録はできるのか
A.公金口座の登録は国への登録となるため、市役所に専用の窓口はございません。Q1のとおりとなります。
※その為、登録した情報等も含めて、公金口座の内容に関することを市役所にお問い合わせいただいても、一切、お答えはできません。
Q4.公金口座の登録を代理ですることは可能か
A.本人の意思により行う必要があるため、ご家族も含めて、代理人による登録は一切認められておりません。
例えば、親の公金口座の登録手続きを子が代理で行うことはできません。ただし、本人が登録を希望する場合で、同席の上で、スマートフォン等の端末操作についてのみを本人に代わって第三者が行うことは可能です。
なお、15歳未満の子の口座登録を行う場合は、法定代理人(=親権者)による登録が可能です。ただし、この場合でも法定代理人以外の代理人が登録することは認められません。
参考:口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約(別ウインドウで開く)(第6条)
Q5.登録できる口座は本人のものか
A.15歳未満の子の登録をする場合も含め、必ず本人名義の口座である必要があります。その為、口座を所有していない方は、公金口座の登録はできません。また、屋号(〇〇会社、など)や肩書(職種)が入っているものも登録はできません。
つまり、八尾 太郎さんが登録できる公金口座の名義は、八尾 太郎(または、ヤオ タロウ)に限られます。なお、通帳を発行しないネットバンク等でも登録ができます。
Q6.公金口座に指定した金融機関の口座の変更等はできるのか
A.マイナポータルから変更や削除ができます。マイナポータルへのアクセスは、ご自身のスマートフォンやインターネット環境よりアクセスをお願いします。
※市役所では変更に関する手続はできません。
Q7.公金口座を登録したくない、または、公金口座は登録しなければならないのか
A.公金口座はあくまで任意の制度ですので、本人が希望しない場合、登録する必要はありません。また、公金口座を登録しないと受け取れない(公金口座の登録が支給要件である)給付金等も2023年2月時点では存在しません。
したがって、制度の趣旨をよく理解いただき、登録をする・しないの判断は、あくまでご自身でその判断を行ってください。
※市役所や公的機関、金融機関から、公金口座への登録を強制・要件とすることは一切ありません。
Q8.制度の事がよくわからない、もっと詳しく知りたい
A.国にてフリーダイヤルが設置されておりますので、下記のフリーダイヤルへお電話ください。なお、市役所では公金口座の一切についてお答えはできません。
Q9.任意の制度なのに、年金事務所などに登録している銀行の口座が強制的に登録されると聞いたが
A.改正番号法により、公金口座の登録をされていない場合、当該行政機関(年金機構や自治体など)より、未登録者に対し「文書」で登録に関する案内の送付があります。この文書を期限内に返送しない(同意や不同意の意思表示をしない)場合にのみ登録に同意したものとみなす制度が予定されております。
つまり、当該行政機関に対し、期限内に登録に同意しない旨を回答(返送)すれば、当該行政機関に提出している口座が公金口座に登録されることはありません。
これは、迅速な公金の給付を実現するべく、政府(国)が導入を目指している制度ですので、当該趣旨をご理解の上、個人の意思表示をお願いします。
公金受取口座登録制度の問い合わせ先
0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)にお掛けいただき、音声ガイダンスに従って「6番:公金受取口座登録制度」を選択してください。
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※市役所では、制度に関する内容はお応えできかねます。
関連リンク
公金受取口座登録制度(別ウインドウで開く) (デジタル庁ホームページ)
公金受取口座の登録支援に関するマニュアルの順守徹底及び登録された預貯金口座の総点検について(別ウインドウで開く)(デジタル庁ホームページ)
公金受取口座の登録支援に関するマニュアルの順守徹底及び登録された預貯金口座の総点検について(別ウインドウで開く)(デジタル庁ホームページ)