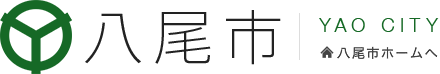- 令和6年度「豊かな老後」作文募集 [2024年7月22日]
- 【参加者募集】金婚式の開催のご案内 [2024年7月22日]
- 地域型介護予防教室(8月申込分) [2024年7月20日]
介護を必要としない体づくりのために
- 家族介護教室(8月申込分) [2024年7月20日]
介護に関する知識や技術を習得するために
- 認知症サポーター養成講座の実施について [2024年7月19日]
- ノルディックウォーキング ~みんなで介護予防~ [2024年7月18日]
ノルディックウォーキングの基礎を学び、自主活動を支援する講座です。(ポール貸出あり)。
- 河内音頭健康体操 ~みんなで介護予防~ [2024年7月18日]
介護予防のための体操「河内音頭健康体操」は、河内音頭のリズムに合わせて楽しく身体を動かすことで、血行促進や平衡機能の改善、運動不足の解消に役立ち、歩行能力を維持・向上できる体操です。健康づくりや介護予防に関するお話と河内音頭健康体操の体験がセットになった健康づくり出前講座のお申込みは高齢介護課まで。
- わかわかごぼうトレーニング ~みんなで介護予防~ [2024年7月18日]
介護予防のための体操「わかわかごぼうトレーニング」は、下肢筋力向上に重点をおいた内容で、ストレッチや筋力トレーニングを組み合わせたプログラムです。健康づくりや介護予防に関するお話とわかわかごぼうトレーニングの体験がセットになった健康づくり出前講座のお申込みは高齢介護課まで。
- 介護(フレイル)予防にもスマートフォンやタブレットを使ってみませんか? [2024年7月8日]
介護予防(フレイル予防)へのスマートフォンなどの活用のご案内です。
- 高齢者見守りサポーターやお [2024年7月5日]
「高齢者見守りサポーターやお」とは、地域のみなさんで高齢者を見守り、何か気がかりなことを感じたら、相談機関(地域包括支援センター・社会福祉協議会など)に連絡して高齢者を支えるしくみです。
- 軽費老人ホーム事務費補助金手続き [2024年7月4日]
- 認知症介護の実践例 YouTube動画の配信について [2024年6月28日]
- 令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります! [2024年6月28日]
- シルバーリーダー養成講座 [2024年6月26日]
八尾市では、65歳以上の人の知識・教養の向上を図るとともに地域福祉活動の実践者を養成するため、「シルバーリーダー養成講座」を開講しています。
- 高齢者の補聴器購入費用の一部を助成します [2024年6月20日]
- いまこそ自宅でも介護(フレイル)予防しましょう [2024年5月31日]
- 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者及び認知症高齢者グループホーム整備事業者の募集について [2024年5月20日]
地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者及び認知症高齢者グループホーム整備事業者募集について
- 高齢者あんしんセンター(八尾市地域包括支援センター)について [2024年5月17日]
高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)は高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らしていけるよう、相談や支援を行います。
- みんなの認知症予防教室 [2024年4月23日]
頭と体を同時に使って脳を活性化させるゲーム形式の認知症予防教室です。
- 在宅医療・介護連携推進事業 [2024年4月17日]
- 後期高齢者医療制度 [2024年4月16日]
- 訪問理美容 [2024年4月1日]
- 高齢者あんしんセンター地区割表 [2024年2月22日]
- 八尾市高齢者ふれあいサロン [2024年2月16日]
高齢者ふれあいサロンは、高齢者などの地域住民が自由に参加できる地域に開かれた集いの場です。市内には住民団体や事業所などが実施するさまざまな高齢者ふれあいサロンがありますのでぜひお気軽にお立ち寄りください。
- やおオレンジカフェ(認知症カフェ) [2024年1月25日]
やおオレンジカフェ(認知症カフェ)
- 介護予防体力測定会 [2024年1月19日]
- 電話音声明瞭器「サウンドアーチ」を寄贈いただきました [2023年11月20日]
- 八尾市内最高齢者へ市長のお手紙をお届けしました [2023年10月12日]
- ジェネリック医薬品を使ってみませんか? [2023年10月3日]
- 令和3年3月31日をもって老人医療費助成制度が終了しました [2023年10月3日]
- 百歳以上高齢者の状況について [2023年9月25日]
- 高齢者ふれあい農園 [2023年5月26日]
- 高齢者肺炎球菌の定期接種について [2023年5月24日]
市では予防接種法に基づき、対象者の方に市内の委託医療機関(要予約)で、高齢者用肺炎球菌の予防接種を実施します。
- 障がい者控除対象者認定書の交付 [2023年4月1日]
身体障がい者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障がい者または特別障がい者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障がい者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告(所得税及び市・府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。 - シルバー人材センターで働きませんか?お仕事を依頼しませんか? [2023年4月1日]
- 家族介護用品支給 [2023年4月1日]
- 軽費老人ホーム運営状況報告書について [2023年3月23日]
軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)の運営施設においては、年4回(7月、10月、翌年1月、翌年4月)『運営状況報告書』の提出をお願いしております。
- 実効性のある避難の確保に関する講演会動画(介護事業者向け) [2023年2月16日]
兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 青田良介 教授による講演動画です。
株式会社あぷり サービス付き高齢者向け住宅あぷり志紀 前田由美子施設長による災害訓練事例報告動画です。 - 生活支援コーディネーターによる「やお地域資源MAP」の作成について [2023年1月13日]
生活支援コーディネーターによる「やお地域資源MAP」の作成について
- 認知症サポーター養成講座について [2022年12月22日]
- 認知症地域支援推進員を配置しています [2022年8月12日]
認知症地域支援推進員
- 生活応援アプリ「やおっぷ」を使った情報発信を始めました [2022年6月13日]
生活応援アプリ「やおっぷ」を使った介護予防教室の情報発信のお知らせです。
- 新型コロナウイルスによる生活及び意識の変化とスマホ等デジタル機器の活用意識調査 [2022年5月9日]
新型コロナウイルス感染防止のため不要不急の外出自粛の長期化により、高齢者が運動不足に陥り、心身機能が低下するおそれがあるという生活上の課題があります。
このたび自粛生活を続けてきた高齢者の状況の把握及び高齢者のICT機器の活用状況を調査することで、「スマホ等を活用した健康づくり事業」の参考とするための基礎的な資料として、本調査を実施いたしました。 - 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) [2022年4月19日]
介護保険法改正により、八尾市では平成29年4月から、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」が始まっています。総合事業では、市町村がそれぞれの実情に応じて多様なサービスを実施できるようになりました。
- 緊急通報システム [2022年4月1日]
急病や火災等の緊急時に、「緊急ボタン」または「ペンダント型発信機」のボタンを押すと受信センター(24時間対応)に連絡が届き、本体スピーカーや電話を通して状況確認を行います。状況に応じて、支援者やご家族に連絡をするとともに、救急車や消防車の出動を要請したり出動員を派遣したりするなどの対応をします。
また、「相談ボタン」を押せば受信センターの看護師や保健師に健康に関する相談をすることもできます。 - 八尾市はり・灸・マッサージ施術事業終了のお知らせ [2022年4月1日]
- 短期集中トレーニングPLUS教室 [2022年3月10日]
要支援1・2の人等を対象に、12回の運動教室と自宅訪問の組み合わせにより、足腰などの機能回復を図る3か月間の集中プログラムです。理学療法士や運動指導士、栄養士などの指導による効果的なプログラムで、元気な自分を取り戻しましょう。
- 八尾市高齢クラブ活動助成金交付 [2022年2月28日]
- 「豊かな老後」作文紹介 [2022年2月4日]
- 第8期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づく公募の選考結果について [2021年12月13日]
- 高齢クラブに入りませんか? [2021年6月18日]
- 社会福祉施設等におけるインフルエンザの予防及び感染拡大の防止等について [2019年1月25日]
- 生活支援コーディネーター [2018年7月26日]
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たします。
- 生活支援・介護予防サービス協議会 [2018年7月26日]
生活支援・介護予防サービス協議会は、生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービスの提供主体の参画が求められることから、市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有および連携・協働による資源開発等を推進します。
- 老人福祉センター [2017年12月27日]
高齢者の各種相談に応じるとともに、健康増進、教養の向上、レクリエーションなど、高齢者が趣味や生きがいをもって楽しく過ごしていただけるように設置した施設です。
- 高齢者を狙った詐欺にご注意ください!! [2017年10月20日]
- 徘徊高齢者家族支援 [2016年4月1日]
認知症などで徘徊のおそれのある高齢者の写真や身体的特徴、緊急連絡先などの情報を市へあらかじめ登録し、徘徊して行方が分からなくなったときに、関係機関が連携して発見協力する「徘徊高齢者SOSネットワーク」を利用して早期発見を図ります。また、家族が希望する場合、FMちゃおの放送で情報提供の呼びかけを行います。
- 成年後見制度 [2016年4月1日]
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分であり、財産管理や福祉サービスの契約などを自分で行うことが困難である人の日常生活を法律的に保護する制度です。
- 認知症について [2014年6月3日]
- 請求関係書類(地域包括支援センター) [2011年1月5日]