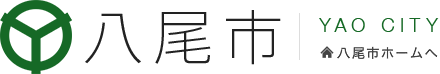[2016年4月1日]
ID:3092
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分であり、財産管理や福祉サービスの契約などを自分で行うことが困難である人の日常生活を法律的に保護する制度です。
例えば、こんなとき後見人が守ってくれます
お金の管理ができなくなったとき
後見人によって預貯金や年金などの財産を管理され、本人以外の人が勝手にお金を使うことができなくなります。
悪質商法にだまされたり、だまされそうなとき
本人がだまされて結んでしまった契約を取り消すことができます。
医療や介護サービスを受ける手続きができなくなったとき
本人の希望を伺いながら、後見人が介護事業者等との契約を行います。また、その後もきちんとしたサービスを受けているかなど、本人の生活を見守ります。
こんな人が後見人になります
家庭裁判所が、本人にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人などから適任者を選任します。
2つの後見制度があります
法定後見制度
判断能力が不十分な場合に、本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが決定されます。
○判断能力が欠けている人には、成年後見人
本人の財産を管理し、本人に代わって契約を交わしたり、本人が交わした契約を取り消すことができます。
○判断能力が著しく不十分な人には、保佐人
借金や相続、家の増改築など重要な契約には、保佐人の同意が必要です。
保佐人の同意を得ずに交わされた契約は取り消すことができます。
また、家庭裁判所に申し立てをして定められた範囲に関して、契約の代理を行います。
○判断能力が不十分な人には、補助人
家庭裁判所に申し立てをして定められた範囲に関して、契約の代理や取り消しなどを行います。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人を契約を結んでおく制度です。
任意後見人は、本人の判断能力が不十分になってから後の財産管理や介護や住まいの確保など、さまざまな契約を行います。
本人の判断能力が確かなうちに、将来判断能力が低下した(例えば認知症になるなど)場合に備えて、あらかじめ後見人と支援内容や方法を話し合い、その内容を公証役場で公正証書にしておきます。そして、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行うと、任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
成年後見制度を利用するには
本人や配偶者、4親等内の親族が申立てを行います(法定後見制度では、身寄りがいない、または音信不通等の場合には、市町村長が申立てをすることができます)。家庭裁判所で書類をもらって記入し、必要書類を添えて提出します。
お問い合わせ先
| 制度についてのお問い合わせ | 大阪家庭裁判所 後見係 電話 06-6943-5872 |
| 申立てをする親族がいないときの相談窓口(高齢者) | 八尾市高齢介護課 電話 072-924-3837 |
| 申立てをする親族がいないときの相談窓口(障がいのある人) | 八尾市障がい福祉課 電話 072-924-3838 |
お問い合わせ
八尾市健康福祉部 高齢介護課 地域支援室
電話: 072-924-3837 ファックス: 072-924-3981