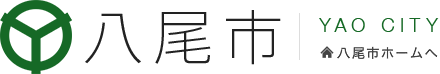[2009年10月1日]
ID:6072
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成21年度第2回産業振興会議
-事務局による司会で次第に沿って進行-
1.開会
2.経済環境部 理事あいさつ
3.議事
-鶴坂副座長による議事進行-
(1)次期総合計画策定スケジュール及び産業振興会議審議経過について
資料1に沿って事務局より説明
(2)次期総合計画における産業政策について
資料2、参考資料により事務局より説明
【質疑、意見等】
委 員:本報告書は次期総合計画期間における産業政策の大きな方向性を示したものであり、個別の事業についての
言及まではないが、総合計画策定部会における委員の皆さんの意見についても読み込むことができる内容と
なっていると考えている。
委 員:世界を相手にするなら海外市場における競争力の強化が必要になってくるが、国際的な競争力のある商品を開
発した市内企業についての新聞記事を以前目にしたことがある。今後、そういった事例を多く世界に発信できる
よう頑張っていただきたい。
事務局:市内には高度な技術力を持った企業は多数あるが、まだまだPRが足りていない部分は多い。今後ものづくりのま
ち八尾としてのブランド化の推進も含め、PRに取り組んでいきたい。
委 員:企業PRについては、八尾市だけでなく、広域的な取組みとして情報発信を進めていった方がより効果的であり、
事業者にとってもメリットがある。また企業立地促進法でも広域的な提案についてはさらに支援を充実させるよう
なことも検討中である。その点も踏まえ今後活用を検討いただきたい。
事務局:例えば東部大阪という括りでは金属加工業が集積している。八尾としての発信、広域としての発信、それぞれが重
要であり今後進めていきたい。
委 員:広域的に取組みを進めることは重要である。中小企業自らが生き残っていくためには新たなものを生み出してい
く必要があるが、八尾市内だけで取組むには限界がある。
企業が開発した商品をどう売り込むか、商業的なアプローチについても、八尾市内だけでなく他地域を取り込ん
で考えていく必要がある。また、広域的な取組みを進める際にはサポートセンターの役割も大きい。広い視野と
ネットワークをもって取組みを進めていただきたい。
委 員:広域的な取組みについて、広域行政体である府としても考える必要がある。海外市場への進出支援をはじめ、八
尾市で実施されようとしている取組みについて、府としてもその思いをどのように取り入れ、東部大阪等でどのよ
うに反映するのか考えていきたい。
委 員:広域連携は進める必要がある。連携のコアが八尾の企業であればなおいい。
委 員:東大阪について言うと、他地域との連携ができていない印象がある。例えば東京での東部大阪をはじめとした府
内の複数の市による展示会でも、東大阪市だけ別枠でやろうとする。
また世界へ通用する商品については、技術も大事だが加えてデザインが非常に大事だと考えている。ブランド力
の強化という点では特にデザインが重要になってくるのでは。例えば愛媛のタオルなどでは技術力とデザインを
合わせて取り組んでいる。
事務局:八尾はソフト部分が弱い。だがそういった点にも取り組む必要はあると考えている。なお報告書の中ではブランド
化の箇所に内包されているということでご理解いただきたい。
委 員:市民の買物について、最近はインターネット上での買物も多くなっている。そういった中、我々消費者としても地域
の商業者と共にどういった売り込み方ができるのか今後考えていきたい。
事務局:特に個別の商業者に対する支援については、あきんどOn-Doネットや商工会議所で発行しているSYAON等で取
り組んでいるが、行政として限界もある。そういったお声はありがたい。
委 員:インターネット上でも実際の購入者の声を参考にして買うことはある。商業者と消費者が力を合わせて売り込むと
いうことは重要。
委 員:若い人はインターネットや生協等で買物をする人が多い。私が住んでいる地域では近くにスーパー等がないた
め、特にそうなっているのかも知れない。昔のように近くに店があり、そこで人が顔を合わせ交流し、生活できる
ような環境になればと思う。
委 員:昨年は環境元年と言われているが、新エネルギー産業やエコカー等、地球環境問題や循環型社会に対しての取
組みをもっと前面に出すべきではないか。
事務局:環境関連産業や自動車産業の関連企業も市内に多数立地しているおり、確かにそういった視点は重要だと考え
ている。なお報告書内の施策の中では「新産業分野への進出」等に含んでいるということでご理解いただきたい。
委 員:「新産業分野への進出」に含むというだけでは弱いのでは。「環境」という言葉をより前面に出していかないと伝わ
らない。
事務局:環境問題に関しては、環境関連ビジネスの創出・成長がある一方、企業が自社の利益だけを考えるのではなく、
環境に配慮した取組みを行うということも求められており、企業にとって大きな課題になっている。また、環境が新
たなビジネスのキーワードとなっているのは事実だが、一方で今後環境以外の新たなキーワードが出てくる可能性
もある。提言書への反映については事務局で検討させていただきたい。
委 員:政府では本年4月に「未来開拓戦略」を発表し、2020年の国の目ざす方向を示している。その中では「低炭素革
命」、「健康長寿」、「魅力発揮」の3つの柱を掲げており、こういった点も念頭に市でも取り組みを進めていただき
たい。
(3)今後の地域商業政策について
資料3および参考資料に沿って事務局より説明。
【質疑、意見等】
委 員:この10年で八尾の産業振興は進んだが、その軸足はものづくりが中心となっていた印象だった。そういった点で、
今回商業の方向性について検討を進められたのは大きい。ところで前回の総合計画策定部会での指摘で、活性
化ビジョンの策定推進について市全体としての方向性を盛り込む必要があるのでは、という意見があったがその
点はどうなっているのか。
事務局:産業部署単独で市全体としてのまちづくりの方向性に関わる部分を定めるのは難しい。今後、各商業者団体にお
いて立案されたビジョン、プランの内容を、市全体のまちづくりに活かして行きたいと考えており、この旨については
報告書のP16に反映させていただいた。
委 員:地域商業活性化アドバイザーの力を借りながら取組みを進めていきたいと考えている。また地域貢献条例等の
検討について記載があるが、大型店ができる中で地域の商業者は衰退してきており、是非八尾市独自の条例の
策定について検討いただきたい。ところで次期総合計画において農業の位置づけなどはどうなるのか。
事務局:この産業振興会議で検討するのは商業と工業のみで農業は含まないが、総合計画全体においてはもちろん農業
も含まれる。その内容については農業委員会(農業振興係)が中心で検討を行うことになる。ただ、農商工連携
等、農業も含めて分野がまたがる内容については産業振興会議でも議論していきたいと考えている。
なお、条例については府では既に設けられたところであるが、府主催の市町村担当者会議の場でも、各市町村で
も同様の条例制定について検討いただきたいという旨の話はあった。ただ、条例となると議会の議決が必要となる
ため、検討という表現にしている。
委 員:市街化区域、市街化調整区域について、それらをなくすという噂を聞いたが、どうなっているのか。新たな住宅が
増え賑やかになるのはいいが、そこに住む人たちは買物をどうしているのか。山手の旧村地域は道が狭いが車
の通行も多くなってきており、都市計画上それらに対してどのように考えているのか。
事務局:市街化調整区域等がなくなるというのではなく、あくまで見直しをするという話である。市街化調整区域の中でも徐
々に市街地化が進んでいるところもあり、見直しは必要。また平成22年度に用途地域の見直しを行う予定。産業と
まちづくりは一体のものとして進める必要があり、工業、商業、農業それぞれを含めてどのようにするべきか考えて
いく必要がある。
委 員:商業調査の結果について示されているが、数字で見る以上に現状は落ち込んでおり、行政からの協力も今後お
願いしたい。
事務局:以前策定部会での議論の中で、「商品を買ってほしいと言うのではなく、一番はじめに見にきてもらいたい。」という
ご意見があったが非常に印象に残っている。そういった流れができるよう我々も考えていきたい
委 員:「地域商業」というもののイメージが、各地域に存在する商店というものから、まちづくりに含まれる形で変わってき
ている。ただ個々の商店がそういう意識を持てるのかについては疑問がある。やはりどこのお店も自己の経営が
第一では。個々の商店に対する施策も打っていく必要がある。また、大型店は便利だからいくというのが消費者の
声であり、商店街にも駐車場などがあれば。どこからどのように人を集めてくるのかという点については、商業者だ
けでは無理だと思う。また、活性化ビジョンについて、各商業者団体からバラバラの内容で出てきたものをまとめ、
市全体としてのものを形作るというのは難しい。お互いの意見を入れながら全体を考えていく必要があるのでは。
事務局:個店への支援については経営革新支援や情報発信支援等実施しているが、行政として支援が難しい部分が多い
ので、大きな方向としては団体への支援を中心に考えている。また個店によるまちづくりについては地域貢献条例
等で示せればと考えている。人をどのように集めてくるのかという点については行政が中心となって検討を進める
必要がある。立地誘導の検討など都市計画と連携しながら進めていきたい。各商店街・市場で抱えている課題、
外部環境等は異なっているため、活性化ビジョンの内容は異なってくる。八尾市の商店街・市場全体の活性化に
ついては、商店会連合会、市場連合会などで情報共有や合意形成を図って取組みを進めていければと考える。
委 員:行政で市全体の内容を作成すべきだというのではなく、商業者団体間でそれぞれの取組みについて情報を共有
し進めていくべきだと考えている。また商業支援についても中小企業サポートセンターで支援ができれば。商品の
販売方法とものづくりは密接に関係しており、その点の機能強化を図ることができれば。広域連携の機能強化も含
め、サポートセンターでの取組みを進めていただきたい。
事務局:サポートセンターは今まで技術的な相談に対する支援が中心であり、その内の8割が生産財に関してのものであ
る。市内企業で消費財を作っているところは少ない。また、広域連携については、けいはんな学研都市等とは既に
連携をすすめている。商業支援機能については今後検討したい。
事務局:「中小企業」サポートセンターなので、工業のみの支援というわけではない。また、今年度から地域商業活性化アド
バイザーを設置しており、商業者団体はもちろん個店への対応についても、産業振興拠点の完成と合わせて、検
討していきたいと考えている。
委 員:まちの魅力発信について、各地域に点在している市の職員の協力を得ながらにぎわいを創出する事業などもでき
れば。また地域の小中高校生を対象とした体験教室等を行うのも一つでは。
事務局:若い世代に地場産業について関心を持ってもらうのは必要。人材確保について、後継者確保は喫緊の課題では
あるが、長期的な視野で考えた際にそういった取り組みは非常に重要である。今後の施策を検討する中で進めて
いきたい。
委 員:行政の担当者は人事異動があるが、仮に担当者が変わっても、今回議論した内容の中で提言書の文言上では
直接現れない部分についても、伝えていけるようにしていただきたい。
事務局:今までの部会および産業振興会議で議論いただいた内容については、全て議事録を残しており、そこで確認はで
きる。また、提言書上においても参考意見という形で残すことができればと考えている。
委 員:市の職員間でまちづくりの中での産業振興の重要性について、認識の相違がないようにするため、この提言書を
用いる等して職員研修のカリキュラムにも含めていただきたい。
(4)その他報告事項について
資料4に沿って事務局より説明
4.産業政策課長あいさつ
5.閉会
※今後のスケジュール
本日各委員より出た意見について事務局一任にて反映し提言書を作成。
9月2日(水)に八尾市長に対し提言書の提出を行う。
以上
添付資料につきましては以下よりダウンロードしてください。
平成21年度第2回産業振興会議
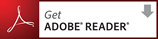 PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。お問い合わせ
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!