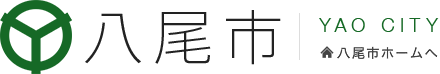[2015年4月1日]
ID:8292
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、HIV感染による免疫機能に障がいのある方に交付されます。
障がいの程度により、1級から7級までの区分があり、1級から6級までが手帳交付の対象です。手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
身体障がい者手帳の交付を受けるには
身体障がい者手帳の申請に必要なもの
○身体障害者診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもので、診断日から3カ月以内のもの。用紙は障がい福祉課の窓口にあります。
(こちらからもダウンロードできます。身体障害者診断書・意見書)
※指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。指定医師については障がい福祉課へおたずねください。
※申請後は返却できませんので、必要に応じて申請前にコピーをとってください。
○写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽・上半身の写真で、ひとり写りのもの。できるだけ最近とったもの。
○個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)
○本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)
以下は非課税世帯の方のみ
○診断書料(文書料)の領収書
非課税世帯の方で、身体障害者手帳診断書の文書料と確認できる領収書(領収印のあるもの)をお持ちの方は、助成が受けられます。
※生活保護を受給されている方は、病院で診断を受ける前に生活福祉課までお問い合わせください。
○本人名義の銀行口座通帳
診断書料(文書料)の助成が決定した際の、振込先確認のためお持ちください。
身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもので、診断日から3カ月以内のもの。用紙は障がい福祉課の窓口にあります。
(こちらからもダウンロードできます。身体障害者診断書・意見書)
※指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。指定医師については障がい福祉課へおたずねください。
※申請後は返却できませんので、必要に応じて申請前にコピーをとってください。
○写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽・上半身の写真で、ひとり写りのもの。できるだけ最近とったもの。
○個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)
○本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)
以下は非課税世帯の方のみ
○診断書料(文書料)の領収書
非課税世帯の方で、身体障害者手帳診断書の文書料と確認できる領収書(領収印のあるもの)をお持ちの方は、助成が受けられます。
※生活保護を受給されている方は、病院で診断を受ける前に生活福祉課までお問い合わせください。
○本人名義の銀行口座通帳
診断書料(文書料)の助成が決定した際の、振込先確認のためお持ちください。
交付申請の手順
1.障がい福祉課で所定の診断書を受け取る
(身体障害者診断書・意見書)
↓
2.指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
↓
3.診断書と必要なものをそろえて、障がい福祉課へ申請する
(各種申請書様式)
↓
4.審査後、手帳を作成
(身体障がい者手帳審査基準についてはこちらから)
↓
5.障がい福祉課で手帳を受け取る
その他の手続き
住所・氏名の変更をされた場合、または手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳と手続きをされる方の印鑑を持参のうえ、障がい福祉課窓口へ届け出てください。
各手続きに必要なもの
| 手続き | 内容 | 顔写真 (たて4cm× よこ3cm) | 診断書 | 手帳 | 個人番号及び本人確認書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 初めて手帳を申請するとき | ○ | ○ | ○ | |
| 等級変更 障がい名追加 | 障がいの状態が変わったとき 他の障がいが加わったとき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 住所変更 氏名変更 | 住所や氏名が変わったとき | ○ | ○ | ||
| 紛失 破損 写真貼替 | 手帳を紛失したとき 手帳が破損したとき 手帳の写真が古くなったとき | ○ | ○ 紛失以外 | ○ | |
| 返還 | 死亡したとき 必要なくなったとき | ○ | ○ |
※新規、等級変更、障がい名追加の申請をされる方のうち、非課税世帯(生活保護世帯を除く)の方につきましては、診断書料助成制度の申請ができます。診断書料の領収書(原本)、ご本人名義の口座がわかるものも併せてご用意ください。
お問い合わせ
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!