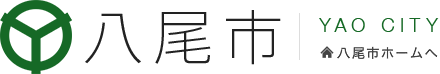[2023年11月11日]
ID:71020
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度八尾きらり【古民家】の登録物件
| 登録番号 八尾きらり | 景観資源の種類 | 景観資源の名称 | 景観資源の所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 建造物 | 岩本同邸 | 大字山畑 | |
| 第2号 | 建造物 | 増田邸 | 東山本町4丁目 | |
| 第3号 | 建造物 | 冨山邸 | 久宝寺3丁目 | |
| 第4号 | 建造物 | 吉川邸(吉は下が長い) | 久宝寺3丁目 | |
| 第5号 | 建造物 | 髙田邸 | 久宝寺5丁目 | 国登録有形文化財 |
| 第6号 | 建造物 | 浅野邸 | 久宝寺5丁目 | 国登録有形文化財 |
| 第7号 | 建造物 | 太田邸 | 久宝寺6丁目 | |
| 第8号 | 建造物 | 太田邸 | 久宝寺6丁目 | |
| 第9号 | 建造物 | 大東邸 | 恩智中町5丁目 | |
| 第10号 | 建造物 | 吉﨑邸(吉は下が長い) | 大字大窪 | |
| 第11号 | 建造物 | 與兵衛桃林堂(板倉邸) | 東本町2丁目 | 国登録有形文化財 |
| 第12号 | 建造物 | 茶吉庵(萩原邸) | 恩智中町3丁目 | 国登録有形文化財 |
| 第13号 | 建造物 | 木村邸 | 東本町2丁目 | 国登録有形文化財 |
| 第14号 | 建造物 | 平田隆夫邸 | 本町3丁目 | |
| 第15号 | 建造物 | 谷山孝邸 | 神立2丁目 | |
| 第16号 | 建造物 | 絹田邸 | 神立2丁目 | |
| 第17号 | 建造物 | 谷山良子邸 | 神立3丁目 | |
| 第18号 | 建造物 | 旧植田家住宅 | 植松町1丁目 | 国登録有形文化財 |
※個人の住宅については、基本的に公開されておりません。見学・鑑賞等で周辺地域を訪れる際には、所有者や近隣住民の方々に迷惑がかからないようにご配慮ください。また、写真撮影やSNSへ投稿される際はご配慮お願い致します。
八尾きらり第1号(岩本同邸)
八尾きらり第2号(増田邸)
八尾きらり第3号(冨山邸)
八尾きらり第4号(吉川邸(吉は下が長い))
八尾きらり第5号(髙田邸)
八尾きらり第6号(浅野邸)
八尾きらり第7号(太田邸)
八尾きらり第8号(太田邸)
八尾きらり第9号(大東邸)
八尾きらり第10号(吉﨑邸(吉は下が長い))
八尾きらり第11号(與兵衛桃林堂-板倉邸)
八尾きらり第12号(茶吉庵ー萩原邸)
八尾きらり第13号(木村邸)
八尾きらり第14号(平田隆夫邸)
八尾きらり第15号(谷山孝邸)
八尾きらり第16号(絹田邸)
八尾きらり第17号(谷山良子邸)
八尾きらり第18号(旧植田家住宅)
八尾きらり登録物件位置図
お問い合わせ
八尾市都市整備部都市政策課
電話: 072-924-3850
ファックス: 072-924-0207
電話番号のかけ間違いにご注意ください!