二六巻 旧植田家資料からひもとく昔のくらし 上 書籍編
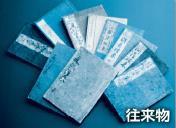
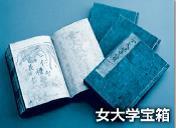
安中新田会所跡旧植田家住宅には、これまで紹介した民具のほかにも多くの資料が残されています。
そのうち今回は、書籍から垣間(かいま)見えた植田家の暮らしの一端についてお話しします。
植田家に残されている書籍は、江戸時代中頃から昭和に至るものまで2000点以上にも及び、版木(はんぎ)に彫って印刷した「版本」や手書きで複写された『写本』が多く見られます。
また、書籍の種類もさまざまで、儒教の教書で特に重要とされる四書五経(ししょごきょう)の中の『孟子(もうし)』や歴史書の『資治通鑑(しじつがん)』『十八史略』といった中国の書物や漢詩集、『日本書紀』や漢字を学ぶ手本となる『千字文(せんじもん)』など学習用のもの、幕末から明治初期の出来事をまとめた『見聞雑誌』『維新見聞記』や紀行文などの読み物、そのほか生け花の本や能、狂言、謡本(うたいぼん)、句集など趣味やたしなみのためのものなどがあります。
中でも『庭訓往来(ていきんおうらい)』『商売往来』『百姓往来』などの往来物と呼ばれる、主に手紙のやりとりの例文から必要なことを学ぶ初級教育用の教科書が目に付きます。
特に『庭訓往来』は江戸時代、寺子屋などで子どもたちがまず最初に勉強するという書物で、衣食住、職業、経営、建築、司法、職分、仏教、武具、教養、療養など、内容は多岐にわたります。
また、女性用の教科書として、貝原益軒(かいばらえきけん)が作ったとされる『女大学宝箱(おんなだいがくたからばこ)』も残されています。
これらはいずれも角が擦り切れていたり、手垢で汚れていたりと使い込まれた様子が見てとれ、子どもの教育に熱心であったことがうかがえます。
もしかすると当時の植田家は、寺子屋のような役割を担っていたのかもしれません。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 観光・文化財課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




















