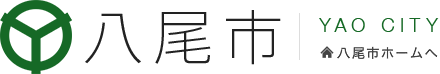[2019年5月1日]
ID:12397
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
同じ人が同じ月に同じ医療機関(入院と外来、医科と歯科は個別に算定)で負担した医療費の額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額
| 所得要件※1 | 自己負担限度額 | 入院時の 食事療養標準負担額 |
| 901万円超 ア | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (多数該当 140,100円) | 460円/1食 |
|---|---|---|
| 600万円超~ 901万円以下 イ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (多数該当 93,000円) | 460円/1食 |
| 210万円超~ 600万円以下 ウ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (多数該当 44,400円) | 460円/1食 |
| 210万円以下 エ | 57,600円 (多数該当 44,400円) | 460円/1食 |
| 住民税非課税 オ | 35,400円 (多数該当 24,600円) | 90日目まで210円/1食 91日目以降160円/1食 |
| 所得区分 | 負担 割合 | 自己負担限度額(入院+外来) (全ての自己負担額を世帯合算) | 入院時の 食事療養費 標準負担額 |
| 現役並み3 (課税所得 690万円以上) | 3割 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) | 460円/1食 |
|---|---|---|---|
| 現役並み2 (課税所得 380万円以上) | 3割 | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) | 460円/1食 |
| 現役並み1 (課税所得 145万円以上) | 3割 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) | 460円/1食 |
| 所得区分 | 負担 割合 | 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額 (入院+外来) (全ての自己負担額を 世帯合算) | 入院時の 食事療養費 標準負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2割 | 18,000円 (8月から翌年7月までの 年間限度額144,000円) | 57,600円 (多数該当44,400円) | 460円/1食 |
| 低所得者2 ※3 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 90日まで210円/1食 91日目以降 160円/1食 |
| 低所得者1 ※4 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円/1食 |
過去12ヵ月の間に3回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目から自己負担限度額は括弧内の金額になります。
〇人工透析をおこなっている慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の治療に
かかる医療費の自己負担限度額は10,000円、ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は
20,000円です。
※上記、疾病の治療にかかった費用と院外処方の調剤費を合わせて自己負担限度額を超えた場合は、ご申請
ください。詳細は特定疾病療養受領証のページをご覧ください。
〇交通事故などの第三者行為による傷病の場合には高額療養費は支給されません。
※1 所得要件…国民健康保険加入者それぞれの、総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計
※2 現役並み所得者…国保に加入している70歳以上の人で、課税所得が145万円以上の人がいる世帯
※3 低所得者2…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※4 低所得者1…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)である世帯
70歳未満の人だけの世帯では…
(1) 自己負担限度額を超えた支払金額を高額療養費として支給します。
同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(2) 21,000円以上(同じ月内)の支払いが複数あれば、世帯で合算します。
同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
70歳以上の人だけの世帯では…
(1) 外来について個人ごとに計算します。
同じ月に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(2) 同じ世帯で外来と入院が複数ある場合は合算します。
同じ月に外来と入院などで複数の受診がある場合は、(1)の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を世帯で合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
70歳未満の人と70歳以上の人がいる世帯では…
(1) 70歳以上の人の外来について個人ごとに計算します。
同じ月に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(2) 70歳以上の人の外来と入院が複数ある場合は合算します。
同じ月に、70歳以上の人の受診が外来と入院などで複数ある場合は、(1)の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を70歳以上の人の受診分だけ合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(3) 70歳未満の人の自己負担限度額と合わせて計算します。
同じ世帯の70歳未満の人の医療機関支払った一部負担金のうち、同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。(1)と(2)との合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
限度額適用認定証について
70歳未満の人
70歳未満の人が高額な医療を受けるとき、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用認定証(ア)(イ)(ウ)(エ)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(オ)」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が自己負担限度額までで済むようになります。ただし、保険料に滞納があると交付ができない場合があります。
70歳以上の人
70歳から74歳までの人は、世帯の所得によって自己負担限度額が決まります。医療費の自己負担限度額を医療機関に示すものになりますので、高額な医療を受けるときには医療機関に保険証・高齢受給者証とあわせて提示してください。
ただし、「現役並み3」および「一般」区分の人は限度額適用認定証が発行されませんのでご注意ください。
交付申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認め印)
届出するところ
健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
〇オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」)がなくても、保険証や初回登録したマイナンバーカードを提示し、医療
機関端末で限度額情報の提供に同意することで、自動的に医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
(保険料を滞納している場合を除く)
オンライン資格確認を導入していない医療機関等の場合、従来通り、限度額適用認定証を提示してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記ページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!