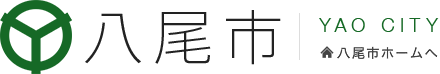[2021年3月5日]
ID:37423
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市には多くの遺跡があり、わたしたちの生活する地面の下にはさまざまな時代の遺物が埋もれています。その中には縄文土器や弥生土器といった有名なものもありますが、まれに変わったものも見つかります。そこで、今回から3回にわたって、市内の遺跡から見つかった「変わったモノ」をご紹介します。
まず、第1回目となる今回は「製塩(せいえん)土器」についてのお話です。その名のとおり、塩を作るための土器で、古代の人々は、土器に海水を入れ、煮詰めて塩を作っていました。土器を砕いて塩を取り出していたため、完全な形で見つかるのはまれで、たいていは割れた状態で出土します。煮詰める際に火を受けた影響で、色は橙色や赤色、灰色をしており、厚さはポテトチップスのように薄いものから、1cmほどの分厚いものまでさまざまなものが見つかっています。
当時の塩作りは、海の近くの集落で行われ、土器に塩が入ったまま内陸の集落に運ばれました。このような塩作りは、地域によりますが、縄文時代から平安時代まで行われていました。
市内では、小阪合(こざかあい)遺跡や木の本遺跡、郡川遺跡で古墳時代の製塩土器が見つかっており、久宝寺遺跡では弥生時代から奈良時代のものも見つかっています。これらの製塩土器は、その特徴から、大阪湾や紀淡(きたん)海峡の沿岸から運ばれてきたものと考えられています。
今でこそ、塩はわたしたちの生活に身近なものとなっていますが、古代においては、食用や馬の飼育に使われていたと考えられ、大変貴重なものでした。
このように、変わった土器からも、当時の暮らしの一端をうかがい知ることができます。

小阪合遺跡出土の製塩土器
【PDFファイル】三八巻 遺跡から見つかる「変わったモノ」 その(1) ~塩作りの土器~

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八尾市魅力創造部観光・文化財課
電話: 072-924-8555
ファックス: 072-924-3995
電話番号のかけ間違いにご注意ください!